注目ベンチャー紹介:CuspAI
2025
.
09
.
15

Written by Ryo Takei
今回の注目ベンチャーの紹介はでCuspAIです。
CuspAIは、AIを活用して「求める性質から逆探索する」ことで新しい材料を発見するプラットフォームを開発する、英国ケンブリッジのスタートアップです。従来は膨大な試行錯誤を要した材料探索を、生成AIとシミュレーション技術の力で数十年から数か月に短縮し、気候変動やエネルギー効率といった社会的課題の解決に直結する新素材の開発を加速します。
CuspAI
サービス/プロダクト概要
- CuspAIは、生成AI(Generative AI)、深層学習(ディープラーニング)、分子シミュレーション技術を駆使して材料設計を効率化するプラットフォームを開発しています。ユーザーが望む特性を入力すると、材料検索エンジンのように膨大な構造を迅速に生成・評価し、精密な機能を持つ新材料の発見を可能にします。
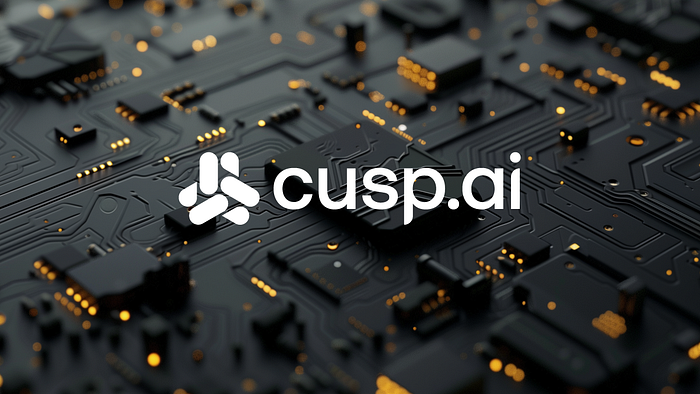
特徴・提供価値
- 研究開発の高速化:同社によれば新材料探索の成功率を従来の約6%から90%へと大幅に向上させるという。発見に数十年かかるとも言われたサイクルを数か月に短縮し、研究開発の効率を飛躍的に高めることが可能。
- 逆探索型のアプローチ:従来の「材料から性質を予測する」流れではなく、「欲しい性質から素材を導く」という逆探索のアプローチを採用。ユーザーの要望を起点に、ニーズに直結した材料設計を行う。
- 炭素回収・貯留分野への応用:同社のプラットフォームは、大気中のCO2を効率的に吸収・放出できる材料を発見し、直接空気回収(DAC)のコストを大幅に低減する。ユーザーが特定の条件下でCO2と選択的に結合する材料をリクエストすると、AIがその条件に厳密に適合する分子構造を生成し、評価・最適化まで行われる。
- 多用途拡張性:CO2回収にとどまらず、次世代バッテリーや半導体の開発、水中の汚染物質を除去する材料、ライフサイエンスまで幅広い分野への応用が可能。AIによって、これまでは膨大な試行錯誤の研究を必要としていた新しい材料や合成経路を迅速に特定することができるという。
ビジネスモデル
- 開発:顧客との合意済みマイルストーンに基づいて研究開発費を受け取り、共同で特定用途向けの新素材を設計・開発する。これにより、開発段階から収益を確保しつつ、顧客ニーズに密着したプロジェクトを推進。
- 商業化:開発した素材が製造・商業化されると、素材の売上に紐づく長期的なロイヤリティ収入を得られる仕組みを採用。知的財産権(IP)は顧客に帰属する一方で、同社は継続的な収益源を確保でき、即時的な開発収入と将来的なロイヤリティ収入の両立を実現する。
なぜ今この会社なのか
- 材料探索のボトルネック解消:従来の材料発見には長くて費用のかかる研究開発プロセスが必要だったが、同社の生成AIモデルは分子構造を設計し、実現可能な合成経路を提案することができるため、開発期間を大幅に短縮することを可能にする。
- 世界経済フォーラムの提言:世界経済フォーラム2024年の「Top 10 Emerging Technologies」(今後3~5年間で世界に最も大きなプラスの影響を与える技術)のひとつとして、AIによる科学的発見が取り上げられた。同社のAI主導の逆探索アプローチは、その方向性に合致する取り組みとして大きな注目を集めている。
顧客・競合・パートナー
- 顧客:大手化学企業Kemira社(フィンランド)が同社のAI検索エンジンを活用し、PFAS除去をターゲットとした水処理材料の開発を行うことを発表(2025年7月)
- 競合:Orbital Materials(AIを活用した新素材開発、AWSと共同でCO2除去材料を試験)、Lila Sciences(AIプラットフォームと自律実験室を構築、科学的発見を自動化)
- パートナー:Meta(旧Facebook)のAI研究部門FAIR、ジョージア工科大学と共同で炭素除去技術に適した吸着材をAIでスクリーニングするOpen Direct Air Capture(DAC)2025データセットを2025年8月にリリース。

こちらの記事に対するお問い合わせやMTGの依頼などはこちらのアドレスからお気軽にご連絡ください。
info@tgvp.vcTGVPは米国を中心としたスタートアップ企業とTOPPANグループの連携を推進しております。



.svg)